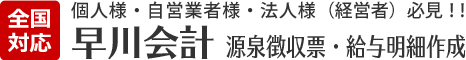給与明細書の作成方法を流れで理解

給与計算とセットで行われるのが、給与明細の作成です。給与明細のテンプレートを掲載しているサイトもありますが、そもそもどんな項目の記載が必要なのでしょうか。
この記事では、給与明細の作成理由から、記載する内容、作成の流れを解説します。
給与明細を作成する理由
給与明細は給与の内訳を記載したものですが、なぜ作成し配布するのでしょうか。
給与明細は賃金台帳などの法定三帳簿とは違い、記載事項や保存期間を法律で明確に定められていません。しかし、所得税や社会保険料、雇用保険料などを給与から控除(天引)した場合、その控除額を「社員に通知する」ことが、健康保険法や厚生年金保険法、所得税法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律により義務づけられています。よって、各控除額を従業員に対して通知するべく給与明細を発行する必要があるのです。
また、給与は口座振込によって支払われるケースが多いですが、口座振込などの場合にはその振込額と以下の項目の記載を含む計算書を従業員に交付する必要があります(平成10年9月10日基発第130号通達)
・基本給や各種手当ての金額(種類別に)
・源泉所得税や社会保険料の控除額(種類別に)
・口座振込みされた金額(最終的な支給額)
この計算内容の通知のためにも、給与明細は作成する必要があるのです。なお給与明細の形態については、紙でも電子データでも問題ありませんので、自社のニーズにあった作成方法を選択しましょう。
給与明細の作成に必要な項目
上述の項目を含めて、給与明細の作成時に記載する項目をまとめると下記になります。
・月の労働時間:出勤・欠勤日数や労働時間数
・支給額:基本給と各種手当
・控除額:健康保険料・厚生年金保険料・(介護保険料)・雇用保険料の控除額
・口座振込額:支給額から控除額を差し引いた額
月の労働時間については、特に法律や通達で明記されている項目ではありませんが、基本給や残業手当の計算に使用される要素です。従業員が支給額が正しく計算されたか確認できるよう、記載しておくのがよいでしょう。
給与明細の作成例

上記の項目を記載した給与明細の例です。給与明細は大きく下記のような流れで作成していきます。
・勤務時間・残業時間を集計して基本給と手当を計算
・税や保険料を計算
・支給額を計算
それでは順を追って、作成方法を見ていきましょう。
給与明細作成の流れ
給与明細の作成は、以下の流れで行います。
1.勤務時間の集計
2.残業代の集計〜計算
3.通勤費等、手当の計算
4.社会保険料の計算
5.課税対象額の計算
6.所得税の計算
7.住民税の計算
8.控除額の記載
9.差し引き支給額の記載
1. 勤務時間の集計
2019年4月より適用された「働き方改革関連法」により、紙のタイムカードやエクセルなどそのような自己申告型での把握は禁止されました。
明確に労働時間を把握する為に、ICカードやパソコンの使用時間など誰にでもわかる客観的記録を基礎として勤務時間の集計を行いましょう。
2. 残業代の集計〜計算
残業代を計算します。時間外労働とは、労働基準法で定められた労働時間を超えて行われた残業のことを言います。
3. 通勤費等、手当の計算
従業員の通勤費を計算します。 公共交通機関を利用する場合、月に15万円までは非課税とすることができます。
4. 社会保険料の計算
健康保険、厚生年金保険、介護保険を計算します。 標準月額報酬に対して保険料率を掛けて、算出します。
※標準月額報酬とは、社会保険料を算出する元となる金額のことで、 従業員の4月、5月、6月の「総支給額」の平均のこと。
5. 課税対象額の計算
「総支給額ー非課税交通手当」が課税対象額となります。
6. 所得税の計算
「 課税対象額ー社会保険料」の金額を「源泉徴収税額表」と照らし合わせて計算します。
7. 住民税の計算
「住民税課税決定通知書」を参照し、住民税を記載します。 自治体によって額が異なってきますので注意しましょう。
8. 控除額の記載
控除額は、「社会保険料+所得税+住民税+生命保険料等」で計算します。
9. 最終的な、差し引き支給額の記載
「総支給額ー控除額」で差し引き支給額が決定します。
源泉徴収票が必要になるとき
源泉徴収票を受け取ったものの、いつ必要になるのかわからない人もいるかもしれません。源泉徴収票が必要になるシーンをご紹介します。
転職するとき

年の途中で転職する際は、前職を退職する際に受け取った源泉徴収票の提出が求められます。これは、前職の源泉徴収と転職先の源泉徴収を合算して年末調整を行うためです。転職の予定のある人は、必ず源泉徴収票を保管しておきましょう。
確定申告するとき

年をまたいで転職する場合や、年収が2,000万円以上の場合、副業収入が20万円を超える場合などは確定申告を行う必要があります。また、絶対に必要なわけではありませんが、住宅ローンを組んだ最初の年や、医療費控除を利用するときなど、確定申告をしたほうが良いケースがあります。
確定申告をする際は、源泉徴収票に記載された内容をもとに書類を作成しますから、源泉徴収票が必要です。
収入を証明するとき

高額のローンを組むときや家族の扶養に入るとき、子供を保育園に入れるときなどに、収入証明として源泉徴収票の提出が求められることがあります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。 ぱっと見では難しく見える給与明細の作り方ですが、 流れは変わりません。総支給額の計算〜控除(マイナス)の計算、 明細への転記の流れで明細を作成しましょう。
毎月の給与の計算と給与明細の作成をラクに
早川会計で行うことで、毎月の給与計算・給与明細の発行が簡単に行えます。