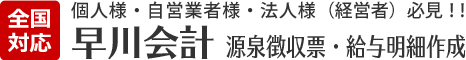給与明細書の作り方。作るのは誰でも出来る

給与明細書は専用のソフトがなくても作成できます。この記事では、給与明細に記載すべき項目や、作成の手順、必要な情報の集め方などをわかりやすく解説します。効率化のコツも紹介するので参考にしてください。
給与明細に記載すべき項目
給与明細とは、給与の内訳を記したものです。所得税法(第231条)では、給与の支払い者は必要項目を満たした支払い明細を受給者に交付することが定められています。給与明細に基本的に記載するのは、以下の4つの項目になります。
●月の労働時間
●支給額
●控除
●口座振込額
労働時間とは、通常の勤務時間、普通残業時間、深夜残業時間、休日残業時間のことです。これをもとに残業手当が計算され、基本給やほかの手当てが加算されて支給総額が決まります。
健康保険や厚生年金などを合わせた金額が控除する金額になり、支給総額から控除を引いた金額が口座振込金額となります。
給与明細の作成に必要なものは?
給与明細に必要な項目を計算するのに、それぞれの金額を決定する情報を集めなければなりません。その情報を集める為には以下のものが必要になります。
1、タイムカード
2、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
3、住民税課税決定通知書
4、健康保険と厚生年金保険の保険額表
5、雇用保険料率表
6、給与所得の源泉徴収税額表
これらのうち、1~3までの書類は必ず必要になるものです。4~6の書類は必須ではありませんがあれば便利な書類になります。
1のタイムカードは勤務状況が分かるもので、会社の勤怠を管理する情報であれば媒体は何でも問題ありません。
2の健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書は、日本年金機構から毎月送付されます。3の 住民税課税決定通知書は自治体に住民税の特別徴収を届け出ると送付されます。
給与明細の作り方!5つの手順で紹介

次に、給与明細を作成する5つの手順を紹介します。
1.勤務時間を集計
タイムカードなどの勤怠の情報からで、実際の労働時間や残業時間を集計します。休日出勤した日数や深夜残業などの時間も集計します。
2.残業手当・通勤手当を計算
集計した勤務時間の普通残業時間、深夜残業時間、休日残業時間を元に残業手当を計算します。通勤手当に関しては、課税対象化非課税対象化も把握しておきましょう。
3.総支給額を計算
基本給に残業手当と通勤手当を加算します。この金額に、会社で定められている各種の手当てを加算したものが支給総額となります。
4.控除額を計算
健康保険、厚生年金保険、介護保険を計算して控除額を計算します。それぞれの計算方法は決められた計算式によって簡単に導き出せます。
社会保険料を計算
健康保険料・厚生年金保険料を計算します。それぞれの金額は標準報酬額をもとにして算出されます。標準報酬額とは、4月、5月、6月の総支給額の平均です。それぞれの保険料は、以下のページに書かれてある表に書かれてある金額になります。
課税対象額を計算
課税対象額と聞くと難しく感じるかもしれないですが、計算は簡単で総支給額から通勤手当と社会保険料の合計を引いたもです。ただし、ここで引く通勤手当は非課税の通勤手当になります。課税対象の通勤手当は対象外です。
源泉所得税を計算
源泉所得税は、上記の課税対象額から社会保険料を引いた金額によって割り出します。税額は国税庁のホームページにある給与所得の源泉徴収税額表から算出します。平成30年度の源泉徴収税額表は以下のページを参考にしてください。
住民税を計算
住民税は自治体から送られてくる「住民税課税決定通知書」にかかれている金額です。もし書類が無い場合には各自治体で手続きをすれば入手できます。特別な計算式があるのではなく通知書に書かれてある金額になります。
5.差引支給額を計算
ここまでで求めた総支給額から控除金額をすべて差し引いた金額が差し引き支給額になります。計算自体は簡単ですが、今まで求めた金額に間違いが無いように注意しておきましょう。
給与明細作成を効率化するには?
これまでの説明で計算自体はさほど難しくないとわかったと思いますが、それでも給与明細の作成には手間がかかってしまいます。ここではその手間を少しでも減らせるように給与明細作成の効率化をどのようにすれば良いかをご紹介します。
給与明細のテンプレートを使用する
給与明細は、支給金額を正確に求められればエクセルなどのテンプレートを利用して簡単に作成できます。ただし、作成した給与明細を従業員に配布するには印刷をして手渡ししなければなりません。
働き方が多様化し従業員がオフィスで仕事をする機会が少くなくなってきているため、手渡しで給与明細を配布することが困難になっています。これらの問題を解決するために給与明細電子化システムを多くの企業が導入しています。
給与明細電子化システムを導入する
発行された給与明細を電子データ化して、従業員に配布するシステムとして給与明細電子化システムがあります。給与明細をメールで配信したり、Webブラウザ経由で確認できるようにしたものです。
これによって会社側は印刷コストも削減できますし、誤って他人の給与明細を渡してしまうリスクも失くせます。 また、従業員にとっても給与明細を紛失してしまう危険性がなく、過去の給与明細をすぐに確認することもできます。
給与明細書が必要になるとき
給与明細書を受け取ったものの、いつ必要になるのかわからない人もいるかもしれません。給与明細書が必要になるシーンをご紹介します。
転職するとき

年の途中で転職する際は、前職を退職する際に受け取った給与明細書の数か月分の提出が求められます。これは、前職の収入と転職先の収入を合算して年末調整を行うためです。転職の予定のある人は、必ず源泉徴収票と給与明細書をセットで保管しておきましょう。
確定申告するとき

年をまたいで転職する場合や、年収が2,000万円以上の場合、副業収入が20万円を超える場合などは確定申告を行う必要があります。また、絶対に必要なわけではありませんが、住宅ローンを組んだ最初の年や、医療費控除を利用するときなど、確定申告をしたほうが良いケースがあります。
確定申告をする際は、源泉徴収票と給与明細書に記載された内容をもとに書類を作成しますから、源泉徴収票と場合によっては給与明細書が必要です。
収入を証明するとき

高額のローンを組むときや家族の扶養に入るとき、子供を保育園に入れるときなどに、収入証明として源泉徴収票と給与明細書の提出が求められることがあります。