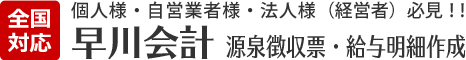給与明細書の作成と保管方法

給与明細とは、雇用契約における労働対価の金額やその内訳を項目別に細かく書き出した文書のことです。一般的に、労働日数や労働時間、残業時間などの給与計算の根拠となる情報と、基本給や手当、交通費などの支給項目とその金額、源泉徴収や社会保険料などの控除項目とその金額、差引支給額、の4種類を記載します。雇用主は、給与を支払う相手へその明細を発行しなければならず、そのことは法律で義務づけられています。さまざまな給与明細に関するテンプレートや書き方についてご説明します。
給与明細に記載しなければいけない項目
給与明細の構成は、大きく分けて3つからなります。1.支給、2.控除、3.差引支給額の3項目です。そして、詳細は下記のとおりです。
1.支給項目
●基本給
●残業代
●勤務時間
●手当(住宅手当、役職手当、通勤手当等)
2.控除項目
●社会保険
●雇用保険
●所得税
●住民税
●財形貯蓄
●組合費等その他会社独自の控除
3.差引支給額
1.支給額-2.控除額=手取り給与額となります。
賞与明細書についても同様に、上記の構成になっています。1.支給項目の箇所が賞与額のみとなりますので、すっきり見えるかもしれません。賞与からも保険料や税金が控除されますので、賞与についても差し引かれた額が支給されます。
給与から控除されている項目について
控除には、法定控除とその他の控除の2種類あります。法定控除とは給与から天引きすることが法律で定められているもので、各種社会保険料や税金がこれにあたります。財形貯蓄や組合費、積立金等は会社が定めているその他の控除ということになります。それでは、法定控除項目について詳しく見てみましょう。
健康保険料
健康保険料は、会社が半額負担しますので、従業員は半額の負担をすれば良いことになっています。その従業員負担額が健康保険料として控除されます。従業員は会社の健康保険組合や協会に加入することで、業務災害以外の疾病やケガ等に関して保険給付を受けることができます。
介護保険料
介護保険料も健康保険料と同様に会社が半額負担します。40歳以上の従業員が被保険者となり、要介護状態となった際に必要な保健医療サービス、福祉サービスに関わる給付を受けることができます。
厚生年金保険料
厚生年金保険料も会社が半額を負担します。会社に勤める70歳未満の人は全員加入しなければなりません。自営や従業員が5人未満の個人会社は国民年金に加入することになります。控除額は、毎月の給与と賞与に共通の保険料率をかけて算出されています。
所得税
所得税は国に納める税金で、1月1日から12月31日までに生じた個人の所得に課税される税金のことをいいます。年収から控除を差し引いた課税所得に対してかかり、税率は課税される所得金額によって異なります。累進課税制度といって、所得が高いほど税率も上がる仕組みです。
住民税
住民税は、地方自治体に納める税金です。前年1月1日から12月31日までの所得に応じて算出される所得割と、一律徴収される均等割を合算した額が税額となります。前年の所得に対しての課税となるため、退職した翌年に仮に無収入であったとしても徴収されるので注意しましょう。
給与明細のテンプレートと書き方
給与明細には労働日数や労働時間、残業時間等の給与計算の根拠となる情報を記載した上で、先ほどの1.支給、2.控除、3.差引支給額の構成で作成します。項目ごとに各種手当や控除明細を明記していきましょう。なお、通勤手当等非課税となるものは別の欄に記載し、区別しやすくしておくと良いでしょう。テンプレートは自動計算が可能なエクセルファイルをオススメします。

給与明細の保管期間について
労働基準法では、法定三帳簿の1つである賃金台帳は3年間の保管義務があります。記載されるべき項目は氏名・性別・賃金計算期間・労働日数・労働時間・残業・休日出勤・基本給・各種手当・控除です。一方、源泉徴収簿や扶養、保険、控除に関わる書類は国税通則法により、7年間の保管義務がありますので注意が必要です。ちなみに個人の給与明細は、確定申告をさかのぼってできる5年間が標準的であると考えられています。
給与証明書について
所得を証明する書類として、所得証明書や源泉徴収票等があり、給与証明と混同しやすいので気をつけてください。給与証明は、勤務する会社でしか発行することができません。支払われた給与を証明する書類です。住宅ローンやカードローンの申し込み、入居審査、帰化申請等さまざまなケースで提出を求められることがあります。どの書類が必要であるのかをしっかり確認してから発行依頼をしましょう。また、社員の配偶者控除や扶養控除の申告を行う際、配偶者・扶養者の勤務先から証明してもらう必要が生じることもあります。
給与証明書のテンプレートと書き方
給与証明には法定の文書があるわけではないので、任意のテンプレートを使用して構いません。給与証明には対象者の入社年月日、氏名、給与として最近の月収と昨年の年収を記載します。給与は支払い年月、支給総額、所得税、その他控除額、差引支給額を明記しましょう。念のため、支給総額には通勤手当等の非課税所得は含めない方が良いかもしれません。含める場合は分けて記載しておくと親切です。給与のほかには、被扶養者の氏名、続柄、生年月日を記載します。テンプレートはワード文書が使いやすいでしょう。
まとめ
給与明細には、支給項目と控除項目の内訳を明記して発行しなければなりません。給与から天引きして社会保険や税金を納税する必要があります。公的機関への証明ともなり得るものですから、遅滞なく正確な労務管理が求められます。テンプレートを利用して、労務管理に役立ててください。
給与明細書が必要になるとき
給与明細書を受け取ったものの、いつ必要になるのかわからない人もいるかもしれません。給与明細書が必要になるシーンをご紹介します。
転職するとき

年の途中で転職する際は、前職を退職する際に受け取った給与明細書の数か月分の提出が求められます。これは、前職の収入と転職先の収入を合算して年末調整を行うためです。転職の予定のある人は、必ず源泉徴収票と給与明細書をセットで保管しておきましょう。
確定申告するとき

年をまたいで転職する場合や、年収が2,000万円以上の場合、副業収入が20万円を超える場合などは確定申告を行う必要があります。また、絶対に必要なわけではありませんが、住宅ローンを組んだ最初の年や、医療費控除を利用するときなど、確定申告をしたほうが良いケースがあります。
確定申告をする際は、源泉徴収票と給与明細書に記載された内容をもとに書類を作成しますから、源泉徴収票と場合によっては給与明細書が必要です。
収入を証明するとき

高額のローンを組むときや家族の扶養に入るとき、子供を保育園に入れるときなどに、収入証明として源泉徴収票と給与明細書の提出が求められることがあります。