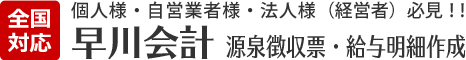給与明細の作り方!記載すべきことと作成手順・効率的に作成する方法

従業員を雇うと、給料の支払いが発生します。給料は、正確に計算したうえで確実に支払う必要があります。ここで気になるのが給与明細についてです。この記事では、給与明細に記載すべき項目や、明細書作成の必要性などについて解説していきます。
給与明細の作成は義務? パートやアルバイトにも必要? 給与明細書の役割とは

まず、給与明細の作成義務についてですが、所得税法において、『給与を支払う者は給与の支払を受ける者に支払明細書を交付しなくてはならない』と定められています。そのため、会社は従業員に給与を支払う際、給与明細書を交付しなければなりません。
給与明細交付の対象者は「支払を受ける者」となっているため、正社員だけでなくパートやアルバイトも対象になります。
また、所得税や社会保険料などを給与天引きした場合は、控除額を従業員に通知することも必要です。給与明細は、その通知の役割も担っているといえます。
さらに、口座振込で給料を支払う場合は、総支給額や控除額、最終的な振込額に関する計算過程を記載することも求められます。給与明細の交付については、書面に限らず、給与の支払いを受ける者の許可を得た上で電子交付でも構わないことになっています。
給与明細に記載する支給項目
給与明細に記載すべき事項は、法律で細かく指定されているわけではありません。しかし、健康保険法や厚生年金保険法に定められている保険料控除額の通知を確実に行うために、記載すべき項目があります。
まず、支給に関する項目です。基本給や残業手当、深夜手当、休日出勤手当、住宅手当、通勤手当などの各種手当、総支給額が該当します。なお、勤務時間は記載する必要はありませんが、給与計算の根拠となる数字であり、給与額の正確性を従業員が確認できるようにするためにも、記載したほうがよいでしょう。
次に、控除に関する項目です。健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料という社会保険料、雇用保険料、所得税、住民税、控除合計額が挙げられます。控除項目については後ほど詳しく説明します。さらに、差引支給額も記載が必要です。
給与明細に記載する控除項目
給与明細には、いくつかの控除項目を記載する必要があります。ここでは、どのような控除項目を記載すればよいか、それぞれの項目の内容も含めて説明します。
健康保険料
1つ目は、健康保険料です。従業員は、健康保険に加入していることによって、医療費の一部を負担することで治療などを受けられるだけでなく、傷病手当金や出産育児一時金の支給を受けることも可能となるのです。加入者である従業員は、会社と折半で保険料を負担する義務があります。
従業員の保険料負担方法は、給与からの控除です。会社は、組合健康保険、協会けんぽのいずれかの適用事業者となっており、それぞれ保険料率が異なっています。
介護保険料
2つ目は、介護保険料です。介護が必要になった場合は、介護保険から介護サービスに関する給付を受けることができます。
介護が必要な度合いに応じて、受けられる給付の種類や金額の上限などが異なります。40歳から64歳までの被保険者が対象となっており、40歳未満の場合は保険料の負担は生じません。
保険料の支払いは、総額を従業員と会社とで折半する仕組みで、この点は健康保険料と同じです。
厚生年金保険料
3つ目は、厚生年金保険料です。厚生年金保険は、国民年金と並ぶ公的年金制度であり、加入していれば国民年金に加えて厚生年金保険からも年金を受けられます。
年金給付の種類は、老後に受け取る老齢厚生年金、障害になった場合に支給される障害厚生年金、被保険者が死亡した場合に遺族に支給される遺族厚生年金などです。
保険料は、会社と従業員が折半することになっており、会社に雇用される70歳未満の従業員が被保険者となります。非正規社員の場合は、1週間あたりの労働時間が20時間以上、1カ月あたりの決まった賃金が88,000円以上などの条件を満たすと加入対象となります。
雇用保険料
4つ目は、雇用保険料です。雇用保険は、労働者の生活や雇用の安定のために国が用意した制度であり、要件を満たせば失業した場合に生活の支えとなる基本手当を受給できます。また、育児や介護などで休業して給与の支払いを受けられない場合などには、育児休業給付金や介護休業給付金などの受給も可能となります。
31日以上の雇用見込みがあり、1週間当たりの所定労働時間が20時間以上である場合は被保険者となり、従業員も保険料を負担します。
保険料は会社と折半ではありません。業種によって料率は異なり、一般の事業に該当する事業所の場合は、会社が約7割、被保険者の従業員が約3割の保険料を負担する仕組みになっています。
所得税
5つ目は所得税です。所得税とは、1月1日から12月31日の1年間において個人に生じた所得に対して課される国税のことです。会社は、雇用している従業員の給与所得の概算額から、概算の所得税を給与天引きする源泉徴収を行います。
そして、年末には確定所得税を算出し、徴収済みの所得税との差額を精算する年末調整を行うことになっています。会社は、従業員本人に代わって、天引きした所得税額を納税する仕組みです。
住民税
6つ目は、住民税です。所得税と同じく、個人に生じた所得に対して課されます。ただし、住民税は国税ではなく地方税です。課税対象となる所得は前年の所得となっている点も所得税とは異なります。
税額は、所得に応じて算出される所得割と、所得に関わらず均等に加算される均等割を合計したものです。会社は、給料から所得税だけでなく住民税も天引きする必要があります。天引きした税額は、従業員本人に代わり、会社が地方自治体に納税します。
給与明細を作るのに必要なもの
給与明細を作成するために必要となるものは、主に3つあります。
1つ目は、出勤簿やタイムカードなど、従業員の勤務時間に関する書類です。
2つ目は、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書です。標準報酬月額とは、給料を一定の区分(等級)ごとに設定した保険料計算用の金額です。この標準報酬月額に対して保険料率を乗じて保険料を計算します。
3つ目は、住民税課税決定通知書です。住民税は、地方自治体が税額を計算する賦課課税方式がとられています。決定通知書に記載されている税額を確認することによって、給与天引きすべき額がわかる仕組みです。
これら3つのほか、「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」「雇用保険率表」「給与所得の源泉徴収税額表」などを揃えておくと便利でしょう。最新版は関係省庁のホームページなどから入手できます。
給与計算の仕方と明細書作成の流れ
給与明細を作成するためには、給与計算を行う必要があります。ここでは、給与の算出方法や給与明細に記載する際の流れについて紹介します。
労働時間の集計と時間外手当・諸手当を計算して総支給額を出す
給与計算を行うためには、まず、総労働時間と時間外労働時間の集計を行います。労働時間に時間単価を乗じて給料を算出するにあたっては、時間外手当の計算に注意が必要です。
時間外手当を計算する場合に使用する時間単価は、通常の単価ではなく割増を行うため、「時間単価×割増率×時間外労働時間」で求めます。また、深夜時間帯の労働や休日の労働に関しては割増率が異なるため、注意が必要です。
次に、給料の総支給額を算出するにあたり、通勤手当や住宅手当などの諸手当を含めます。「基本給+諸手当+時間外手当」で総支給額を算出します。
社会保険料の計算
与計算にあたっては、各種社会保険料の計算も欠かせません。健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険の保険料を計算します。
健康保険や介護保険、厚生年金保険の保険料については、標準報酬月額を求めたうえで適用されるべき各保険料率を乗じて算出します。雇用保険については、雇用保険法に定められている賃金額を計算したうえで、所定の料率を乗じて求めることが必要です。
算出した各保険料は、給与明細の該当欄に記載してください。なお、各保険料は、従業員本人が負担する分のみを記載します。
税金(所得税・住民税)の計算
給与計算をするにあたり、所得税と住民税の計算も重要な要素です。所得税額の計算においては、まず課税対象額を確定させることから始めます。
課税対象額は、「総支給額-非課税支給額(非課税の通勤手当や社内規程に基づいて支給される出張手当等)」です。年末調整で対応できない控除項目については各従業員が確定申告で対応することになるため、給与計算を行う会社としては、前記計算式によって課税対象額を求めることができます。
所得税は、課税対象額から社会保険料をマイナスした金額を国税庁の源泉徴収税額表と照らし合わせれば算出可能です。住民税は、市町村から送付される住民税課税決定通知書を参照して計上します。
控除額と総支給額の記載
給与明細作成においては、給料から控除される項目ごとの金額と合計控除額も記載します。控除される項目は、税金や社会保険料だけでなく会社を通じて契約している生命保険料等があればそれも含まれることに注意が必要です。
また、社内預金の積立を行っている場合は、その積立額なども控除対象となります。そのため、控除額合計は、「社会保険料の合計+所得税+住民税+生命保険料等」となります。
さらに、差引支給額も記載します。差引支給額は、「総支給額-控除額」です。最終的に、差引支給額が従業員の給与支払口座に振り込まれることになります。
給与証明とは?給与証明の作り方
従業員から給与証明の発行を求められた場合、給与明細とは別に、給与証明を作成するケースもあります。給与証明は、従業員が住宅ローンを組む場合や賃貸住宅への入居をする場合に、金融機関や貸主から所得証明書類として提出が求められることがあります。
給与証明は、勤務先の会社が発行するものです。発行様式などは法律で定められているわけではありません。一般的な記載事項は、最近の給与月額や前年の年収、支払い年月、支給総額、所得税、その他控除額、差引支給額などです。ネット上で公開されているテンプレートを利用して作成してもよいでしょう。
給与明細を効率的に作る方法
多くの資料を集めて給与明細を正確に作成するのは、手間がかかる作業です。そこで、給与明細を効率的に作成する方法をいくつか紹介します。
ワードやエクセルのテンプレートを使う
1つ目の方法は、ワードやエクセルのテンプレートを活用する方法です。インターネット上には、普段使用しているワードやエクセル用の無料テンプレートがあります。それらのテンプレートをダウンロードして必要項目を入力すれば、比較的簡単に給与明細を作成できるでしょう。
給与明細作成だけを目的にする場合は、低コストですぐにでもできる点がメリットです。ただし、このあと紹介する別の方法と比較すると、「給与計算作業を個別に行う必要がある」点がデメリットとなります。
アウトソーシングする
2つ目の方法は、給与明細作成作業のアウトソーシングです。アウトソーシングとは外部のソースを利用することです。給与明細作成を請け負ってくれる業者は多数あり、外部に作業を委託すると、必要な情報を手渡すことを除けば、ほとんどの作業を自社で行わずに給与明細作成を行うことが可能です。
従業員の増加等などによって給与計算が負担になっている場合や、コストや手間を削減したい場合、外部に給与明細作成作業を任せて従業員は本来の業務に集中したい場合には有効な選択肢の1つだといえます。ただし、アウトソーシングにかかる費用が高額になりやすいというデメリットがあることも念頭に置いておきましょう。
給与明細作成システムを利用する
3つ目の方法は、給与明細作成システムを利用して給与計算や給与明細作成を自社で行う方法です。たとえば、『やよいの給与明細 オンライン』を利用すれば、給与計算が比較的簡単にできるだけでなく、保険料率や税率等に関する頻繁な法改正にも自動で対応してくれるため、エクセル利用などにはない安心感があります。また、人為的な作業ミスも防げるでしょう。
コストも前述のアウトソーシングより低いですし、サポートも手厚く、操作に不安を感じる人にも安心です。さらに、クラウドシステムであるため、常に最新の法令に基づいて給与計算ができる点も大きなメリットとなります。
給与額のミスは許されない!正確に計算して振込・通知を
給与に関する知識不足や明細書の作成ミスは、従業員に不信感を与えることにつながります。法令に準拠しない計算方法などによって本来支払うべき給料の支払いができなければ、大きな問題になる可能性もあるでしょう。そのため、給与明細を作成するにあたっては、最新の知識に基づき正確な計算を行える体制を整えておくようにしましょう。
給与明細書が必要になるとき
給与明細書を受け取ったものの、いつ必要になるのかわからない人もいるかもしれません。給与明細書が必要になるシーンをご紹介します。
転職するとき

年の途中で転職する際は、前職を退職する際に受け取った給与明細書の数か月分の提出が求められます。これは、前職の収入と転職先の収入を合算して年末調整を行うためです。転職の予定のある人は、必ず源泉徴収票と給与明細書をセットで保管しておきましょう。
確定申告するとき

年をまたいで転職する場合や、年収が2,000万円以上の場合、副業収入が20万円を超える場合などは確定申告を行う必要があります。また、絶対に必要なわけではありませんが、住宅ローンを組んだ最初の年や、医療費控除を利用するときなど、確定申告をしたほうが良いケースがあります。
確定申告をする際は、源泉徴収票と給与明細書に記載された内容をもとに書類を作成しますから、源泉徴収票と場合によっては給与明細書が必要です。
収入を証明するとき

高額のローンを組むときや家族の扶養に入るとき、子供を保育園に入れるときなどに、収入証明として源泉徴収票と給与明細書の提出が求められることがあります。